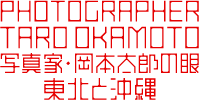写真家・岡本太郎 −「対極主義」の眼
飯沢耕太郎 (いいざわこうたろう:写真評論家)
岡本太郎は、日本人にはむしろ珍しい万能型のアーティストである。絵画はもちろん、彫刻、書、陶芸、建築など、さまざまな分野の作品を残している。また著述家としての才能は、ベストセラーとなった『今日の芸術』(光文社、1954)をはじめとする著作を読めばすぐにわかるだろう。
だが、彼が「写真家」でもあったことは、まだあまり知られていないかもしれない。僕自身も岡本太郎が1950〜60年代にかけて、大量に撮影していたことを知ったのは最近になってからである。その総数は、日本を撮ったものだけに限っても1万3千カット以上、韓国、インド、メキシコ等の外国の写真を加えれば2万カットを超える。量だけではない。その質においても、彼の写真は同時代の他の写真家たちの仕事にひけをとらないどころか、時にはそれらを凌駕するようにすら思える。
岡本太郎の写真の存在が注目されるようになったのは、1996年の彼の没後である。1999年10月に開館した川崎市岡本太郎美術館の開館記念展「多面体・岡本太郎」には、「写真ー撮す」というパートが設けられ、約50点の写真が展示された。2001年4月には同美術館で、土門拳、濱谷浩、東松照明らの写真との対比を試みた「日本発見ー岡本太郎と戦後写真」展が開催された。2002年8月の「岡本太郎が見た沖縄」(那覇市民ギャラリー)も、ユニークな構成の写真展として話題を集めた。
この間、岡本敏子編『岡本太郎の沖縄』(NHK出版、2000)、岡本敏子・山下裕二編『岡本太郎が撮った「日本」』(毎日新聞社、2001)、岡本敏子・飯沢耕太郎編『岡本太郎と東北』(毎日新聞社、2002)といった写真集も次々に刊行され、時ならぬ「太郎写真」ブームが起こりつつある。これから先も、このたぐいまれな眼力の持ち主が渾身の力で撮影した写真群は、多くの人々の心をとらえていくのではないだろうか。
岡本太郎が写真の面白さに目覚めるのは、1930〜40年のパリ滞在時代である。この時期のパリでは、マン・レイ、ブラッサイ、フローランス・アンリといった彼と交友関係のある写真家たちが、前衛的な写真表現の可能性を模索しようとしていた。特に名作『夜のパリ』(Paris de Nuit,1933)で知られるハンガリー(現ルーマニア領トランシルヴァニア)出身のブラッサイとは親しい間柄で、撮影についてのアドヴァイスを受けたり、引伸し機を譲り受けたりしたこともあったようだ。このパリ時代に、きわめて正統的な写真についての素養を身につけたことが、のちの「写真家」としての経験に生かされていくことになる。
戦後になって、岡本太郎は文字通り「多面体」的な活動を展開していった。彼がふたたび写真に取り組むようになるのは、1956年から開始される縄文土器の撮影によってである。いうまでもなく「縄文」という古代日本人の生命力あふれる造形美の発見は、岡本太郎の芸術観を大きく変えた出来事だった。プロ写真家が撮影した土器の写真に飽き足らなかった彼は、ついに自ら撮影を開始する。その「激しく追いかぶさり重なり合って、隆起し、下降し、旋回する流線紋」(「縄文土器論」『みづえ(旧字)』1952年2月号)を超クローズアップでとらえた写真群には、被写体に向かって大胆に踏み込んでいく彼の撮影のスタイルがよくあらわれている。
だが、「写真家・岡本太郎」の真骨頂を示しているのは、『芸術新潮』(1957年4月〜12月号)に連載された「芸術風土記」(のちに『日本再発見ー芸術風土記』新潮社、1958として刊行)と、『中央公論』(1962年11月号、63年4月、10月号、64年6月号)に掲載された「神秘日本」(のちに『神秘日本』中央公論社、1964として刊行)の両シリーズであろう。この「現代日本のありのままの姿から芸術の問題を掘り起こす」(「あとがき」『日本再発見ー芸術風土記』)ために全身全霊でぶつかっていったルポルタージュにおいて、彼自身が撮影した写真はきわめて重要な役目を果たしていた。単純に原稿執筆のための資料というだけでなく、そこには被写体となる現実との出会いに対する驚きと感動があふれ出している。おそらく彼自身、現像・プリントされた写真をあらためて見直すことで、新たな角度から思考の筋道を辿ることができたのではないだろうか。
もう一つ、沖縄で撮影された写真も重要である。沖縄には1959年と66年の二度訪れ、36枚撮りネガシート85本に及ぶ大量の写真を撮影している。この時の写真は『中央公論』(1960年3月〜5月号、7月、11月、12月号)に掲載された「沖縄文化論」(のちに『忘れられた日本ー沖縄文化論』中央公論社、1961として刊行)におさめられ、彼のスケールの大きな沖縄論に豊かな彩りと確かな説得力をつけ加えた。「芸術風土記」や「神秘日本」でもそうなのだが、「かえって日本の内側 −−むしろ閉され、忘れさられ、現代生活の外に押しやられている、原型のようなものにひきつけられる」(「あとがき」『忘れられた日本ー沖縄文化論』)という彼の志向は、沖縄のような「悠久に流れる生命の持続」を感じさせる場所で、より輝きを増しているように思えるのだ。
1950年代から60年代にかけて、岡本太郎は旅から旅の生活を送っていた。「芸術風土記」の連載では秋田、長崎、京都、大阪、岩手、松江、徳島、高知などを訪れ、「神秘日本」では青森、高野山、出羽三山、広島、熊野などを撮影した。その合間に沖縄だけでなく、フランス、イタリア、アメリカ、メキシコ、韓国などにも出かけている。アーティストとしても著述家としても、最も脂が乗り切った時期であり、止めどなく湧き出てくるエネルギーが、充実した仕事として結晶しているように感じられる。
先に述べたように、この時期には日本だけでも1万3千カットに及ぶ写真が撮影されている。岡本太郎美術館に所蔵されているそれらの写真のコンタクト・プリントを何度か通して見ているうちに、その中でも特に目を強く引きつけるパートがあることに気づいた。それこそが本展のテーマである東北と沖縄の写真である。もちろん、他の地域でも傑作といえる写真がたくさん残されている。しかしこの両地域に関していえば、その内容においても密度においても、他を圧倒するような凄みすら感じてしまうのだ。
それがなぜなのかを考える前に、東北と沖縄の撮影旅行の概略をふりかえっておくことにしよう。
東北の秋田へは「芸術風土記」の第一回として1957年2月12日〜16日に訪れた。夜行列車で秋田駅に着き、「はじめてみる冬の裏日本、そのきびしい気配」に「身のしまる思い」を感じている。まず「非常に素朴で明朗」な秋田の風俗に触れ、男鹿半島の「なまはげ」の行事を取材する。鬼の面をシャーマニズムの仮面と結びつける視点は、パリ時代に人類学者マルセル・モースに傾倒した岡本太郎の面目躍如といえるだろう。秋田では他に大曲の綱引き、横手の朝市、「ぼんでん」、「かまくら」などを撮影している。
岩手を旅したのは1957年6月15日〜18日で、当地出身の画家、村上善男の勧めによるものだったようだ。「縄文」の伝統を引き継いだ「馬の文化」が、今なお息づいているかを確かめるという狙いがあった。岩手ではまず平泉の中尊寺を訪ね、鹿の角を加工した護り刀の柄飾りに「エゾ模様」の気配を見い出す。小岩井農場では、既に馬の放牧がなくなりかけているのに落胆するが、種畜場でダイナミックな種付けのシーンを撮影することができた。さらに花巻で「鹿踊り」と「鬼剣舞」を見て、その「人間が動物を食い、動物が人間を食った時代」を彷佛とさせる迫力ある舞踏に感嘆している。
青森には「神秘日本」の取材で1962年7月21日〜27日に滞在した。この時はまず恐山でイタコの口寄せを取材し、その夜、誰ともなしに始まった婆さんたちの盆踊りに「大河の幅のようにおし流されてきている彼女らの生命力」を感じとる。次いで一ノ渡の獅子舞、川倉の「地蔵盆」、金木の「荒馬」などの芸能や民俗行事も撮影している。また孫内の「淡島さま」、八戸の「オシラさま」のような「神おろし」の場面では、まるでモータードライブ付きのカメラのような連続シャッターを切ってり、彼がその神秘的な雰囲気にのめり込んでいる様子が伝わってくる。「イタコ、そして東北全体の自然をオシラの気配がおおうている。...それは私の身体をとおって、日本人全体の生甲斐に響いているように思われる」。これが青森の旅で得た岡本太郎の結論であった。
沖縄滞在(1959年11月16日〜12月2日)は、旧友たちの招きで実現し、当初は骨休みの観光旅行のはずだった。ところが、初めて訪れた沖縄に岡本太郎は完全に魅了されてしまう。「それは私にとって、一つの恋のようなものだった」と『忘れられた日本ー沖縄文化論』に記しているが、軽い旅のエッセイのつもりだった『中央公論』の連載も、予定をはるかに超える分量に膨れ上がっていった。この時の旅では、忙しい日程を割いて沖縄本島だけでなく、「のろ」の信仰が受け継がれている久高島、八重山諸島の石垣島、竹富島にも足を伸ばしている。
その過程で、日本人の思想、文化、宗教の原型を、沖縄の舞踊、歌謡、宗教行事、人々の暮らしのあり方などを通じて探り出そうとした。特に、久高島の神域である「大御嶽(ルビ:うたき)」のたたずまいに、「なんにもないということ、それが逆に厳粛な実体となって私をうちつづける」という「神と人間の交流の初源的な回路」を見い出す思考の冴えはスリリングであり、岡本太郎の洞察力の鋭さがよくあらわれている。この「大御嶽」のしんと静まりかえった光景をとらえた写真は、「写真家・岡本太郎」の仕事の中でも、最も印象に残る一枚といえるだろう。
沖縄には、久高島で12年に一度おこなわれる女性たちのイニシエーションの儀式「イザイホー」を見るために、1966年12月に再訪している。嵐をついて小舟で上陸してようやく間に合った「イザイホー」は、厳かでありながら「ふと色めく」こともある魅力的な儀式だった。ここでも岡本太郎は、何かに取り憑かれたように連続シャッターを切り、神の下へと誘われていく女たちの姿をつぶさにとらえようとしている。自らもシャーマン的な気質を持つ彼にとって、舞踊や宗教儀礼のようなトランス状態にある者を撮影するという行為は、とりわけ心躍らせるものだったのではないだろうか。
なぜ東北と沖縄の写真が、他の地域にはあまり見られない不思議な魅力と生命感を湛えているのか。そのことについて考える時に、「対極主義」という概念が重要になってくるのではないかと思う。
「対極主義」とは岡本太郎が1947年頃から提唱しはじめたもので、芸術家の基本的な姿勢とは、対立する二つの要素をそのまま共存させることであるとする主張である。たとえば「無機的な要素と有機的な要素、抽象・具象、静・動、反発・吸引、愛憎、美醜、等の対極が調和をとらず、引き裂かれた形で、猛烈な不協和音を発しながら一つの画面に共生する」(『アヴァンギャルド芸術』美術出版社、1950)ということだ。その両極の反発によって、火花が散り、「生々しい、酸鼻を極めた光景」が出現する。「しかしそれに怖じず、逆に勇気を持って前進し、ますます引き裂かれ行く、そこにこそアヴァンギャルド芸術家の使命がある」と彼は強調するのである。 この「対極主義」は岡本太郎の生涯を貫く芸術観となった。「写真家」としての仕事においても、やはりその姿勢は明確に保たれている。「芸術風土記」でも、「神秘日本」でも、あるいは「沖縄文化論」の取材でも、彼が訪れたのは大きな矛盾に引き裂かれた土地が多かった。1950〜60年代においては、現代のように日本全体が均質化しておらず、たとえば「表日本」と「裏日本」では、人々の暮らしにおいても、文化や伝承においても、極端なコントラストが存在していたことを忘れてはならないだろう。いうまでもなく、その矛盾が最も激しくぶつかり合い、不協和音を発していたのが東北や沖縄である。だがそのような聖と俗、陰と陽、内と外、貧しさと豊かさとがカオス状に混在し、衝突しあって、異様な軋み声をあげているような場所こそが、「対極主義者」岡本太郎を最もエキサイトさせるのである。
その意味では、東北と沖縄という二つの土地のコントラストもまた興味深い。日本の北と南、気候はもちろん歴史や文化においても、両者はまったく引き裂かれている。にもかかわらず、岡本太郎の写真を見ていると、この二つの土地が奇妙に混じりあい、区別がつかなく思えてくるのは僕だけだろうか。「オシラさま」や「イザイホー」のような宗教儀式だけでなく、人々の貌つき、表情、身振りなどから滲み出してくる気配、その大地に根ざした生命力が共通しているように感じられるのだ。
東北と沖縄は、東京や京都のような政治・文化の中枢から見れば周縁に属する地域である。だからこそ、逆に時の流れとともに押し流され、雲散霧消してしまった日本文化の古層=原型が、しぶとく保たれてきたともいえそうだ。岡本太郎のカメラ・アイは、それらをいきいきと、きわめて具体的なイメージとして定着している。ここでも対立物の共存を通じて現実世界の構造を把握していくという「対極主義」の眼が、見事に貫かれているといえるだろう。
考えてみれば、写真という表現メディアそのものが「対極主義」の具現化でもある。岡本太郎は土門拳との対談で、「写真というのは偶然を偶然でとらえて必然化することだ」(「今日の芸術」『カメラ』1954年11月号)と語ったことがある。写真家がいかにきちんと構図を定め、シャッタースピードを計算して「決定的瞬間」を写しとろうとしても、偶然にファインダーの中に飛び込んできた要素が、彼の思惑を裏切ってしまうことがよくある。だが岡本太郎は、そこにこそ「写真の今日の芸術としての凄みがある」と喝破するのである。矛盾を矛盾のまま平然と呑み込んで、画面の中に同居させてしまう写真の本質的なあり方を、これほど徹底して使いこなした「写真家」は、他にあまりいないのではないだろうか。
岡本太郎の写真についての調査・研究は、まだまだ始まったばかりである。今後、さまざまな形でその豊かな遺産を生かしていく道が探られなければならないだろう。東北と沖縄という彼の写真の白眉といえるイメージ群を集成した本展が、その一つの契機となることを、そして彼の写真の魅力がより多くの観客の方々に共有されることを心から願っている。 (いいざわ・こうたろう:写真評論家)