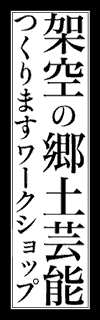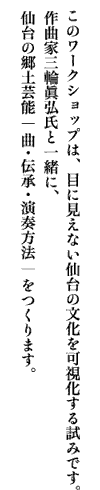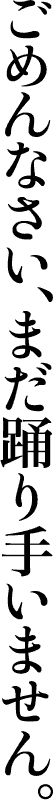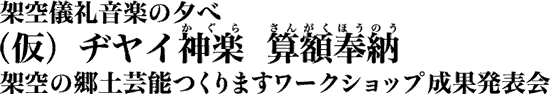仙台市内の神社に代々伝えられ、住民たちに毎年親しまれている伝統の舞がある。 この郷土の祭りが、江戸時代において画期的な先進性を誇っていた高等数学の 結晶である、という事実が明らかになり、歴史家らの間に波紋を呼んでいる。
江戸時代、鎖国下の日本では和算とよばれる独自の数学が発達し、その水準は今日 のレベルに照らしても高く、複雑なものであった。多くの人の集まる神社仏閣には 算額(さんがく)とよばれる学者の研究成果を記したものが奉納され、他の学者 たちのさらなる切磋琢磨の助けとなった。全国で多数の和算流派が生まれ、東北 においては一関田村藩に和算塾を開き多数の門下生を抱えた千葉胤秀(ちばたね ひで/関派の和算家)一派がとくに有名である。
胤秀の弟子の一人に、神童と謳われた鷹嘴侍相之介(たかのはしじあいのすけ/ 現在の塩竈市出身)という者がいた。彼はわずか7歳にして和算の難問を次々に 解き明かし、当時の算額奉納最多記録を塗り替えたという逸話が残っている。 が、そのあまりに斬新すぎる知性は、同門の和算家たちにすら誰一人理解できない レベルに達し、神社への算額奉納も異端として拒否されるようになる。侍相之介 21歳の年、ついに胤秀から破門を言い渡されるに至り、失意の侍相之介はいずこ へともなく失跡した。後の生死は不明であった。
近年再評価の機運が高まっている侍相之介であるが、2001年、仙台市の愛宕神 社末社に奉納されていた郷土舞踊手本の版木から驚くべき発見があり、「その後 の侍相之介」を知る有力な手掛かりに研究者らはさらなる意気込みをみせている。
発見された版木は当時には珍しく3枚の板をベニヤ板のように貼り合わせたもの で、表面には舞踊のステップや楽譜が刻まれている。ところが板の接着面をX線 撮影した結果、当時の和算術とも西洋数学ともまったく異質な算額の図面が姿を 現したのである。
この版木の作者は高橋蛇居(たかはしじゃい)といい、地域の子供にときおり算盤 や歌を教えていた人物、と当時の記録にはある。普段は集落の外れに隠れ住む偏屈 な老人であったが、ムラの実益に役立つため意外に住民からは慕われていたよう である。蛇居の名の由来は蛇が多数出没する、常人のあまり近づかない土地に 住んでいたことからそう呼ばれたという。
筆跡鑑定や材料の年代測定により、高橋蛇居こそは若くして胤秀一門を追われた 鷹嘴侍相之介その人であると判明した…
※この伝承はフィクションであり、歴史上及び実在の人物・機関等とは一切関係 ありません。 また、このワークショップは現在も継続中であり、 インターネット上で上記のような伝承についても制作中です。 演奏会までの間に内容が変更されることもありますので、あらかじめご了承ください。
最新の情報はこちらにアクセスしてください。
http://www.smt.jp/geinou/