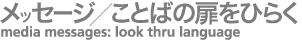
ワークショップ
「復活!カッパン印刷会社」
せんだいメディアテーク5階ギャラリーの活版印刷機の部屋にて、
2月24日(土)と25日(日)の二日間、ワークショップ「復活!カッパン印刷会社」が行われました。
塩釜市の渡辺印刷所さんからご寄贈いただいた、現役を退いたもののまだちゃんと働く活版印刷機と、
仙台市の針生印刷株式会社さんからご寄贈いただいた活字を使って、
参加者が自分だけのオリジナルカードをつくりました。
24日は14人の、25日は13人の参加者とともに、
長時間にわたってわいわいと創作活動をした模様をお伝えします。
- 活版印刷ってなあに?

15世紀にグーテンベルグが鉛活字による活版印刷技術を実用化したことにより、
印刷による情報の大量生産が可能になりました。
出版された無数の本はもちろんのこと、
活字技術そのものがひとつの大切な文化を形成していたことも忘れることができません。
しかし今、コンピュータによる情報伝達技術の急速な発展によって、
数世紀にわたる主役の座を譲り渡そうとしています。
メディアテークは、古いメディアが培ってきた大切な文化をひとつひとつ掘り起こしながら、
未来の情報発信を考えていきたいのです。今回はその第1回目、メディアテーク・カッパン印刷会社のデビューです。
- どうやって印刷するの?

今日のワークショップは、原稿つくり、文選、植字、印刷という作業に分かれています。
カッパン印刷会社社員(本日の講師)の菊地淳さんが、流れや注意点を説明します。
このメディアテーク・カッパン印刷会社の「一日社員」になった参加者のみなさん。
エプロンと名札をつけて、工場にいる気分。
- カードをデザインしよう!
 印刷する際の原稿を作ります。
印刷する際の原稿を作ります。
社員(本日の講師)の伊藤奨さんが、本日のカードのパターンと色分け、
文字の配置などについて、わかりやすく説明します。
自分の名前・住所や「おめでとう!」などの自由文、イラストなどを考えます。
- 紙を選ぼう
一口に「紙」と言っても、世の中にはとても多くの種類の紙が存在します。
今回カードをつくるにあたっては、10種類の紙を用意しました。厚い紙、柔らかい紙、白くて質感の異なる紙、
銀色に輝く紙、柄の入った紙。どんな紙を選ぶかによってインクののりなど仕上がりが異なります。


- いよいよ文選(ぶんせん)
原稿を見ながら活字を探して文選箱に並べて行く作業のことを「文選」と言います。
文選をする際は、活字の大きさ毎にまとめて文選します。
文選場では、活字の配列は基本的に部首順にならんでいます。
ケースの分類は使用頻度によっても分けられています。
自分の名前、見慣れた漢字。それでも活字を拾ってくるのに、人によっては15分もかかります!





- 植字(しょくじ)をしてみる

植字とは原稿により文選をした活字をデザインや割付しながら組版をすることを言います。
植字をするための作業机を「植字台」と言います。その他に植字用器材として罫切りやインテル切り・輪郭削りなどがあり、
材料としてインテルやクワタなどを使って組版をします。
これは自分ひとりでするのは難しい!活字職人さんに手伝ってもらいます。
カッパン印刷会社社員(本日の講師)鈴木久雄さんの見事な手さばき!



- 活版印刷機で印刷

組版が終わったらいよいよ印刷です。活版印刷では活字がそのまま版になりますので、
版を印刷機に取り付けるためチェースという枠に版の組み付け作業を行います。
印刷機は用紙サイズにあわせた各種の設定を行ったり、暖機運転をしながらインクをローラーに巻いて準備を整えます。
社員の印刷工(本日の講師)小松勇さんは、長年培った技術で私たちを驚かせました。



- 色替えをします
今回は金赤(日の丸のあか)・群青(深いあお)・紫・草(みどり)の4色の中から、一枚のカードに2色を使いました。
印刷の色を替える際は、一度ローラーを洗ってきれいにします。
新しいインクを入れて機械が回り出すと、ローラーに色が一気に広がって、きれい!



- つくったカードを展示しました
みんなのカードを見せ合いっこ。交換会に発展します。
今回のワークショップで作ったカードは、3月20日まで展示「メッセージの博物誌」会場で見ることができます。


- 記念撮影
午後1時30分から午後8時30分まで、25日は午後7時30分まで、長い間楽しくがんばった社員のみなさんで、記念撮影です。
社員の井上彩さん、柴田真夏さん、原田紀子さん(メディアテーク・ボランティア)も笑顔いっぱい!


[←ワークショップ紹介へ]
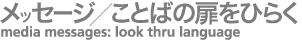
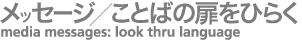


 印刷する際の原稿を作ります。
印刷する際の原稿を作ります。




















