2023
03 02
メディアテーク開館
仙台市民図書館開館
コラム 2024年09月27日更新
会員寄稿文「わたしにとってのドキュメンタリー」Vol.7 我妻和樹
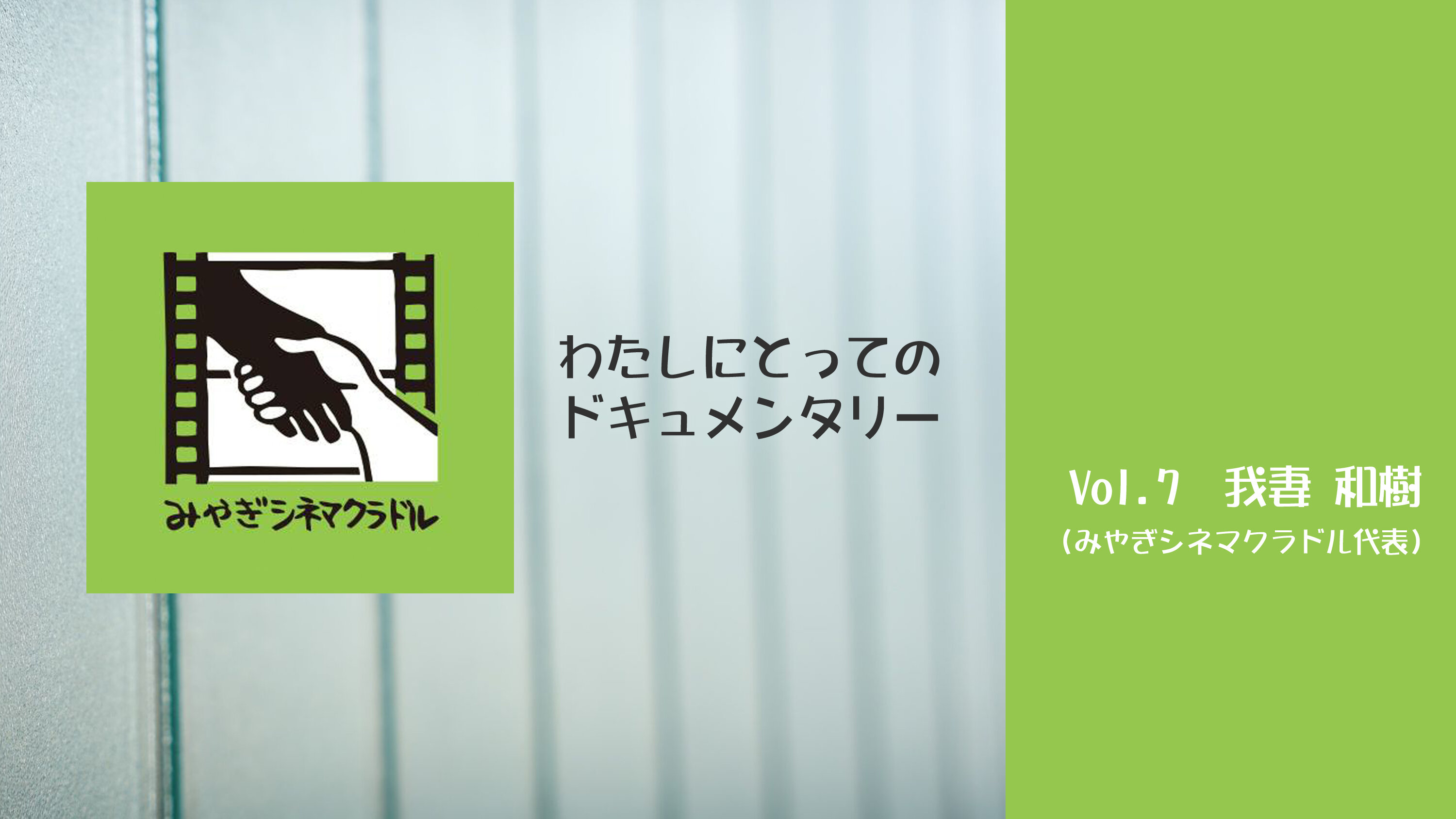
※この企画は、みやぎシネマクラドルの活動をより理解していただくことを目的として、「わたしにとってのドキュメンタリー」をテーマに会員が自由に文章を書く企画です。
**********
僕がドキュメンタリーという表現手法に魅力と可能性を感じるのには大きく二つの理由があります。
まず一つは、映像記録そのものの力です。
例えば、何気ない日常や非日常の出来事、変わりゆく風景やそこにあった思い、大切な人の表情や声―。映像には、そこに確かに存在していたかけがえのない時間や生の輝きを、そのときの温度のままに半永久的に記録し、観る人の心の奥深くにある感情に直接働きかける力があります。ドキュメンタリーにおいて、この映像が持つ本来の力は何よりも重要な要素です。
そしてもう一つは、現実世界の想像を超える複雑さと、現実に生きている人の圧倒的な存在感を可視化する力です。
僕は、ドキュメンタリーにおいて必ずしも社会批判的なテーマ性が最重要事項とは思っていません。ドキュメンタリーの定義を「事実の断片を作り手の意図によって再構成した映像」とするならば、それによって生み出される作品は実に多様です。
しかし、知られざる現実や人の葛藤など、普段あまり目を向けられることのないこの世界の繊細で複雑な側面を、ほかでもない作り手自身の身体を通じて可視化し、社会に問いかけることも、ドキュメンタリーの大きな役割です。そこに映り込む情報の豊かさは、劇映画ではとても再現できないものであり、それは昨今のAIでも生成できない独特の領域といえます。そしてここにドキュメンタリーの大きな可能性があります。
ただし、ドキュメンタリーの場合、自分の中に「撮りたい・描きたい・伝えたい」という強い動機があったとしても、それは撮影対象となる人の同意があってはじめて成り立つことです。ドキュメンタリーが事実そのものではなく、作り手の表現物=創作物=フィクションとはいっても、それは対象の意思も人生も、作り手の都合で好き勝手にできない厳然たるものであるという大事な前提があるからです。
そのため、すべて作り手の望み通りとはいかなくても、表現が互いにより良く生きるための方法として活用されることが、ドキュメンタリーにとっては大事なことなのです。
このように、ドキュメンタリーは僕自身がこの世界や人とどう関わり、何を思ったかの記録ともいえます。ときには「自分が受けた衝撃や感動の10分の1も描けていない」と思うこともあります。
その一方で、現実との対話から生まれる新たな何かが、思いもよらぬ奇跡や幸福を呼び起こすこともある。それが僕にとってのドキュメンタリーです。
**********
我妻和樹(あがつま・かずき)
1985年宮城県白石市出身。主な作品に、宮城県南三陸町を舞台にした長編ドキュメンタリー映画『波伝谷に生きる人びと』(2014)『願いと揺らぎ』(2017)『千古里の空とマドレーヌ』(2021)など。みやぎシネマクラドルでは2015年の立ち上げから代表を務め、震災10年を機に当会で制作したオムニバス映画『10年後のまなざし』(2021)にも参加。令和3年度宮城県芸術選奨新人賞(メディア芸術部門)受賞。