2023
03 02
メディアテーク開館
仙台市民図書館開館
コラム 2024年09月12日更新
「ドキュメンタリー制作ノート」第6回:試写(対象への確認を含む)
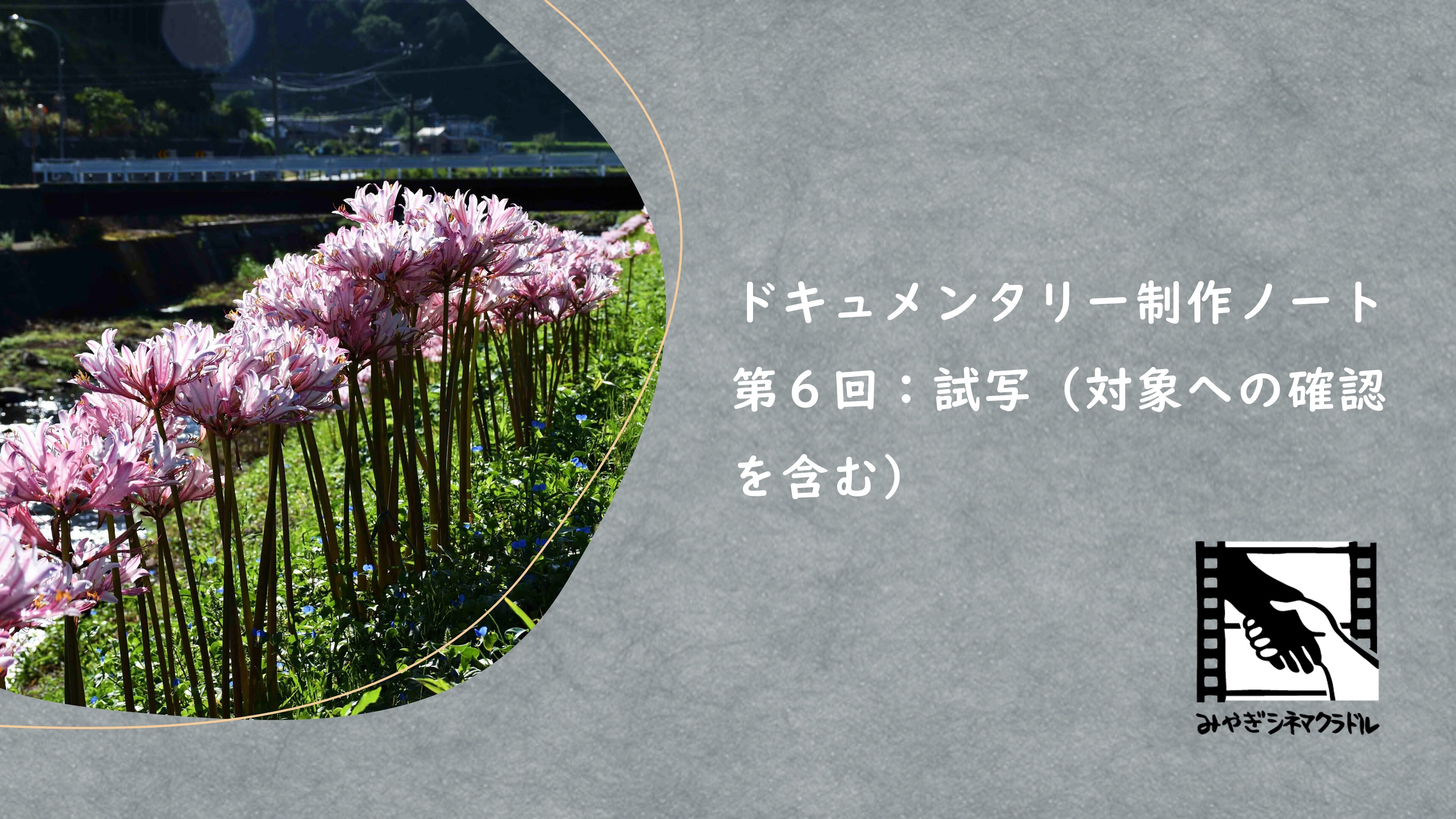
※この企画は、ドキュメンタリー制作における一つ一つのプロセスについて、テーマごとにみやぎシネマクラドルの作り手が文章を執筆する企画です。2024年度の1年間で以下のテーマについて執筆する予定です。
第1回:企画・テーマ設定
第2回:撮影交渉
第3回:撮影準備
第4回:撮影
第5回:編集
第6回:試写(対象への確認を含む)
第7回:発表(自主上映会・劇場公開を含む)
第8回:完成後の対象との関係
第9回:失敗談
第10回:フリーテーマ
ドキュメンタリーを制作中の人、これから制作しようと考えている人の参考になれば幸いです。
なお、現在、みやぎシネマクラドルの会員がドキュメンタリーへの思いを自由に執筆する「わたしにとってのドキュメンタリー」も連載中です。そちらも是非ご一読ください。
**********
「ドキュメンタリー制作ノート」第6回:試写(対象への確認を含む)
■我妻和樹(あがつま・かずき)
ドキュメンタリーにおいて、編集した作品を撮影対象に確認してもらい、発表の同意を得るプロセスは絶対に欠かせません(制作の途中で対象が亡くなってしまった場合には、ご家族など身近な人の同意を得ることが必要になります)。
何故なら、ドキュメンタリーが事実そのものではなく、作り手の創意工夫に満ち溢れた創作物=フィクションだとしても、そこに映っているのはまごうことなきその人であり、作り手が勝手にやりたいことのリスクをもっとも引き受ける可能性があるのは対象だからです。
このリスクについて、「人を描く行為そのものの問題」と「対象の実生活への影響」という2つの側面から考えてみます。
まず、当然ながら、作り手が描きたい(伝えたい)対象のイメージと、対象の思うそれが常に合致するとは限りません。そこでは作り手がどれだけ誠心誠意対象と向き合っていても、描かれる当の本人との間には必ずズレが生じます。
例えば、作り手が解釈した対象の姿や意図を持って構成したストーリーに、当の本人は「違う、そうじゃない」と違和感を覚えるかもしれません。また、作り手にとっては重要なシーンが、対象にとっては実生活を揺るがす脅威になるかもしれません。
このように、描く側が描かれる側の事情や繊細で複雑な思いのすべてを想像するのには限界があります。そしてもし対象の思いを置き去りにして、単なる素材として利用したならば、それは不本意なイメージを対象に押し付け、言葉を奪い、大義の元に搾取し苦しめるゆゆしき事態となってしまうでしょう。
だからこそ、作り手は対象の思いを受け止め、あらゆるリスクを想定し、発表前にきちんと対処する必要があるのです。
ここで重要なのは、作り手と対象が互いのズレを認識した上で、対話によって新たな学びや創造性に繋げていくことです。もしかしたら、互いに意図を伝え合うことで、対象は自分では気づかなかった自身の映像の魅力に気づくこともあるかもしれませんし、作り手も単なる妥協ではない、作品をより良くするための方法を見つけることもあるかもしれません。そして、そこに信頼できる第三者の客観的な視点が加わることで、議論が円滑に進む場合も往々にしてあります。
そうして「フィクションだけど本当のこと」と信じられる物語を作り手と対象が互いの納得の上で共有し、対象が自らのイメージを肯定できる状態になってこそ、はじめて作品を世に発表することができるのです。
■海子揮一(かいこ・きいち)
スクリーンに投影された私の横顔を見て、私たちは「私たち」になる。
編集した映像のチェックはアトリエの120インチのスクリーンに投影して行うようにしている。完成した映像はスクリーン以外でもモニター、スマホの画面、液晶テレビなどいろいろな装置と環境で視聴される可能性があるのだが、なるべくスクリーンでの鑑賞を判断の基準としている。その理由はまず単純に画面の大きさと視野角が違うことだ。音声もヘッドホンではなくスピーカーを通して聞く。映像の鑑賞とは体験であり、その基準点をどこに置くかで体験の質と量が変わる。また、スクリーンに投影して観るとモニターで気がつかなかったところが見つかることも多い。そして体験だけでなく風景や登場人物の印象も大きく変わってくるため、それを元に編集を見直すことになる。
なぜ人は、映像をどのように鑑賞し目に入れるかで受ける印象や思考が変わってくるのか...。「メディア論」のマーシャル・マクルーハンの説では、透過された映像とスクリーンで反射された映像を目に入れた時の脳の働きに違いが出るという。実験により、液晶モニターのように透過光を直接見ると人は情緒的に情報を受け取り、一方スクリーンからの反射光で見ると理性的に情報を分析するようにモードが切り替わったという結果となったそうだ。想像するに、なにかに投射した光や情報を見るというのは情報(映像)の社会化と深く結びついているのではないか。洞窟の薄暗い火の明かりで見る壁画のように、集団で共有している物体に絵や記号を記録したり鑑賞することは、その集団にとっての神話・記号・言葉と呼応していき、それが固有の文化のゆりかごとなるのではないか。その数万年前の洞窟での共有体験を現代でも映画館という形式として残していると思うと面白い。
これは出演していただいた方を招いての試写でも同様の感想があるようで、映像に出てくるご自身あるいはご家族の姿や声をスクリーンという「共有された壁画」として鑑賞すると、自他の境界が揺らぐような体験になるようだ。自分を日常の主観ではなく、社会的に見るという視点の違いが、試写において映像の世界を受容する第一歩になるのだろう。「撮影交渉」の段階で示していた、撮影者と被写体との共作という理念と関係がスクリーン上にそのまま形となって現れることも含めて、この受容の度合いを測ることがドキュメンタリー映像特有の、試写というプロセスの核心なのかもしれない。
■村上浩康(むらかみ・ひろやす)
編集を終えてまずしなければならないのが、被写体となってくれた人への試写です。たとえ自分では納得できる作品になったと自負していても、被写体ご本人の意見を確認することは何より重要です。事実関係に間違いが無いか、ご本人の発言の意図を誤認してはいないか等、確認して頂くことが沢山あります。そして作り手としては、ご本人が作品をどう感じたのかが一番気になります。
ただご本人としては、映像を通して初めて自分を第三者の視点から見せられるので、たいていは冷静に見ることが出来ません。自分がどう見えているのか、何かおかしなことを言っていないか、みっともない部分や見てはほしくないところが映っていないかなど、様々なことが気になり平常心では見られないのが普通です。
もちろん作者である私も、事前にご本人が嫌がるであろうことや、誤解を招くような表現は回避して編集をしていますが、ドキュメンタリーはその人のいいところや都合の良い点だけを描くものでなく、時にはご本人にとっては見られたくない部分も映し出す必要があります。なぜなら、そこにその人の葛藤があり、それが社会への投げかけや疑問となり、見る人へ綺麗事だけではない現実味をもたらすからです。
そうはいっても、この点をご本人に理解してもらうのはなかなか難しいことです。先述の通り、観賞直後のご本人は冷静な精神状態ではないのですから。
そういった時、私はなるべくもう一人、作り手や被写体とは異なる視点で見てくれる第三者の同席をセッティングします。それもご本人になるべく近しい人、例えばご家族やお友達、映画の協力者に試写を一緒に見てもらうのです。
観賞直後のご本人は自分が他の人にどう映るのか、とても不安になっています。その時に、作り手である私がいくら説明しても、それは弁明としか受けとってもらえません。しかし往々にして、同席した人の感想は一般的なものとして素直に受けとめてくれます。
例えば同席者が「よく映ってるね」とか「いい映画になったね」と少しでもポジティブな言葉を発すれば(そう言ってもらうには作品の質が問われますが)、ご本人はそういうものかと少しは納得してくれます。つまりは安心するのです。
試写の席に第三者に同席してもらうことは、被写体の方に安心して頂くと共に、作品を理解して頂くための大切な手立てとなります。そして被写体の方から頂いた意見は貴重な助言にもなります。
**********
<執筆者プロフィール>
■我妻和樹(あがつま・かずき)
1985年宮城県白石市出身。主な作品に、南三陸町を舞台にした長編ドキュメンタリー映画『波伝谷に生きる人びと』『願いと揺らぎ』『千古里の空とマドレーヌ』など。みやぎシネマクラドルでは2015年の立ち上げから代表を務める。令和3年度宮城県芸術選奨新人賞(メディア芸術部門)受賞。
■海子揮一(かいこ・きいち)
1970年宮城県大河原町出身。建築家/ブリコルール/クリエーター。環境とコミュニティをテーマにした建築設計活動の傍ら、映像製作・イベント企画・造形デザインも手掛ける。より自然に近い環境を求めて、2018年より仙台市に隣接する村田町寒風沢の古民家に拠点を置く。
■村上浩康(むらかみ・ひろやす)
宮城県仙台市出身。2000年よりドキュメンタリー映画の製作・監督を続けている。主な作品に『流 ながれ』(文部科学大臣賞)『東京干潟』(新藤兼人賞金賞)『蟹の惑星』(文化庁優秀映画)『たまねこ、たまびと』(2023キネマ旬報文化映画ベストテン第3位)など。新作『あなたのおみとり』を2024年劇場公開予定。