2023
03 02
メディアテーク開館
仙台市民図書館開館
コラム 2024年10月25日更新
「ドキュメンタリー制作ノート」第7回:発表(自主上映会・劇場公開を含む)
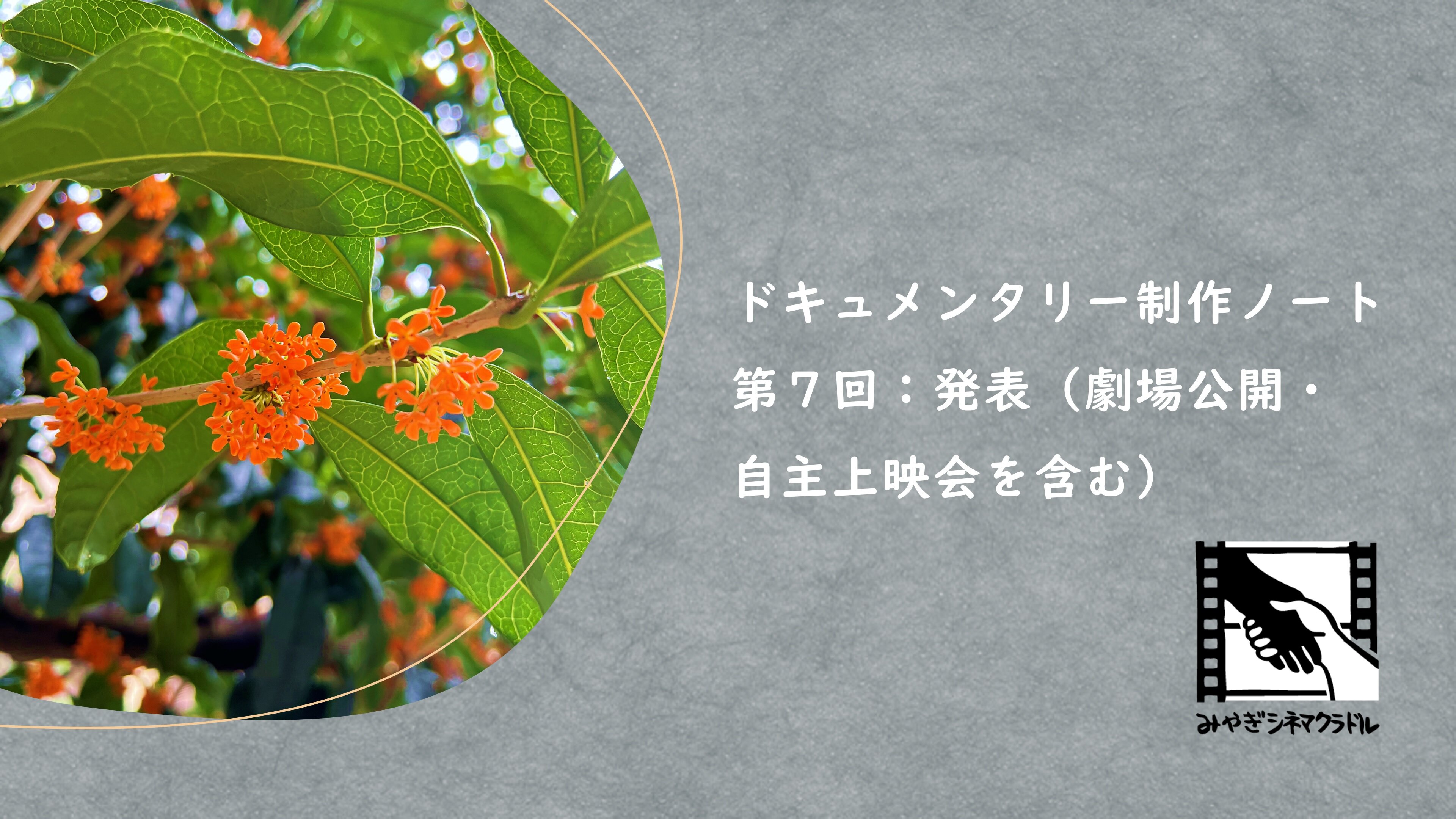
※この企画は、ドキュメンタリー制作における一つ一つのプロセスについて、テーマごとにみやぎシネマクラドルの作り手が文章を執筆する企画です。2024年度の1年間で以下のテーマについて執筆する予定です。
第1回:企画・テーマ設定
第2回:撮影交渉
第3回:撮影準備
第4回:撮影
第5回:編集
第6回:試写(対象への確認を含む)
第7回:発表(自主上映会・劇場公開を含む)
第8回:完成後の対象との関係
第9回:失敗談
第10回:フリーテーマ
ドキュメンタリーを制作中の人、これから制作しようと考えている人の参考になれば幸いです。
なお、現在、みやぎシネマクラドルの会員がドキュメンタリーへの思いを自由に執筆する「わたしにとってのドキュメンタリー」も連載中です。そちらも是非ご一読ください。
**********
「ドキュメンタリー制作ノート」第7回:発表(自主上映会・劇場公開を含む)
■我妻和樹(あがつま・かずき)
前回は、対象に編集した映像を確認してもらい、対象自らが気持ちを整理することの重要性について書きました。
対象は、自分が映った映像を「映画」として観ることで、それが社会に対して何かしらの意義を持つものになることを自覚します。つまり自分の姿が不特定多数の他者に開かれることを改めて意識するのです。
そこでは当然さまざまな不安もありますが、気持ちを整理することで対象が自らの言葉で作品について語れるようになり、「何を言われても、どう見られても大丈夫」という覚悟のようなものが定まっていきます。作品は一度発表したら作り手や対象の意図を超えてさまざまな受け止められ方がされるため、そのための心の準備が必要不可欠なのです。
また、最後の撮影から時間が空いている場合、試写をした上で、最後に対象の現在の姿を追加撮影するなど、作品のテーマをより深めるための撮影も可能になります。この段階になると、対象は作り手の意図をしっかり理解してくれているため、より良い作品にできるよう、積極的に協力してくれる場合もあります。
こうして対象との間にある種の共同関係を築き、やれることをすべて尽くした上で、いよいよ作品を発表する段階となるのです。
ドキュメンタリーは終始対象にお世話になりっぱなしです。通常の撮影では対象にお金を支払うことはないので、対象は、作り手がやりたいことに無償で付き合ってくれるいわばボランティアのようなものです。作品の発表も、それは社会に何かを問いかけ、何かを還元することが目的であって、対象には直接的には利益が無いことです。
とはいえ、作品を観てくれた人が対象に好意的な言葉を投げかけたり、新たな縁が生まれたりなど、それによって対象の人生に何かプラスになるものがあれば、作り手にとってこんなに嬉しいことはありません。その意味では、作品の発表というのは対象に対する恩返しでもあるのです。
一方で、対象の同意がどうしても得られない場合もあります。ドキュメンタリーは制作に長い時間を要するため、対象の社会的立場や生活環境、考え方の変化などによって、撮影開始時点での合意が変わってしまう場合もあります。
そのときは、対象の気持ちを第一に考え、発表を諦めるしかありません。「伝えることの大切さ」や「知ることの大切さ」のために誰かの尊厳(意思や権利)を蔑ろにしてはいけないということを、作り手は肝に銘じておかなければならないと考えます。
■海子揮一(かいこ・きいち)
映像制作は私の大切な仕事のひとつだ。
仕事というのは誰からか何かを受け取り、「私」を通した後に、また別の誰かに手渡すことではないか。リレーのバトンのように。上の句が書かれた連句のように。送り出した相手が何かを手放し、受け取る「私」にその解釈や取り扱いを委ねなければこの流れは途絶えてしまう。「私」の作品もまた解説や言い訳や作り直しを諦め、受け手の誰かに委ねなければならない。それが果たされてようやく仕事が完成する。つまり仕事の終わりは始まりであり、受け取り、受け渡す先の人たちとの信頼関係をどう築くのか、あるいは裏を返せばどこまで諦められるのかを作り手は常に問われている。
私は宮城県大和町で開催されている「吉岡宿にしぴりかの映画祭」に2016年から実行委員として参加し、映画の作り手と受け手の橋渡しに携わってきた。映画の選定からパンフレットの校正などの企画と準備を経て、上映当日に観客と作品が出会う瞬間に立ち会うのはいつも胸が熱くなる。小さな劇場なので観客と監督の距離が近いのも魅力だ。しかしその手作りのシアターの裏側では、ほとんどが普段は映画以外の職業であるスタッフが監督と観客の期待に応えなければというプレッシャーと闘っている。そうした多くの人々の尽力で場が作られ、その声と眼差しによって映画というメディアに体温が生まれる現場を見ると、いつかはこういう場で私の作品が上映される日を夢見てしまう。できるかぎり多くの手で作品世界を受け渡すことが、小さな物語や声を伝えるにはとても望ましい。
しかし中には自主上映会に不慣れな方々が主催者となり、視聴に支障あるような場所で上映されたり、当日になって驚いたり慌てたりすることもある。スクリーンが小さい、外光が漏れる、解像度が低いプロジェクターしかなかった、スピーカーとアンプという存在を知らなかった、プレーヤーが古すぎたなど、冷や汗をかきつつ様々な助けを借りて乗り越えてきた。かつては主催者に作品上映のすべてを委ねるのが潔いと考えていたが、いまは上映用の機材を自前で用意し、主催者の想いに応えるためにも少しでも上映の環境づくりに最善を尽くそうと認識を改めた。
それは冒頭で述べた通り、撮影をさせていただいた方々から委ねられた物語や眼差しを、観客にきちんと届けることが仕事であると考えているからで、迷った時にはその基本に立ち戻るようにしている。
■村上浩康(むらかみ・ひろやす)
映画製作の最終目標は作品を上映してお客様に見ていただくことにあります。映画には監督やプロデューサーという作り手がいますが、彼らが必ずしも自分の作品を一番理解しているとは限りません。
特にドキュメンタリーはゼロから世界を作るのではなく、現実世界を切り取って作品化するので、製作者が意識していないことも映し出されることがあります。映画を見たお客様から、思いもよらないことを指摘され「そういう見方もあるのか」と逆に教えられることもしばしばです。実は作り手にとっては、それが醍醐味です。「作品は観客が完成させる」とよく言われますが、本当にその通りなのです。
作品の公開形式について私の場合は、子供の頃から映画が好きで、当時は「映画は映画館で見るもの」と相場が決まっていたので、まずは映画館での公開を目標にしています。とはいえ、私が製作している所謂「自主製作映画」は必ずしも映画館で上映してもらえるとは限りません。上映の可否は各映画館のスタッフの判断に委ねられます。
この映画が公開するに足る公共性があるか、興行的に集客が見込めるか、作品として世に問えるかなど、様々なハードルをクリアして初めて劇場公開が叶います。
作り手にとって劇場公開のいい点は、やはり大きなスクリーンと良い音響で作品を観てもらえること。そしてお客様が、わざわざ出向いて自分の作品の為に時間とお金を割いて観て下さる(つまり映画への向き合い方がより真剣で積極的である)という点にあります。
上映後には舞台挨拶をさせて頂く場合もあり、そこではお客様から質問を受けたり、感想を伺うことも出来て、直接作品を届けたという実感が得られます。
もう一方でドキュメンタリー映画上映の重要な形態が、自主上映会です。自主上映会の有難い点は、劇場公開ほどの規模で見ていただけはしませんが、主催の皆さんやお客さんと親密に交流できるところです。上映後の質疑応答やディスカッション、また打ち上げや交流会に呼ばれた場合には、膝を突き合わせて作品について語り合う事が出来て、作り手として様々な意味で得られるものが大きいのです。
劇場公開も自主上映会も、それぞれに作り手にとっての意味があり、すなわちそれは、送り出した作品が受け止めてもらえたという実感が得られること、それが次なる製作の励みや課題となり、作り手としての自覚を新たにすることに繋がるのです。
**********
<執筆者プロフィール>
■我妻和樹(あがつま・かずき)
1985年宮城県白石市出身。主な作品に、南三陸町を舞台にした長編ドキュメンタリー映画『波伝谷に生きる人びと』『願いと揺らぎ』『千古里の空とマドレーヌ』など。みやぎシネマクラドルでは2015年の立ち上げから代表を務める。令和3年度宮城県芸術選奨新人賞(メディア芸術部門)受賞。
■海子揮一(かいこ・きいち)
1970年宮城県大河原町出身。建築家/ブリコルール/クリエーター。環境とコミュニティをテーマにした建築設計活動の傍ら、映像製作・イベント企画・造形デザインも手掛ける。より自然に近い環境を求めて、2018年より仙台市に隣接する村田町寒風沢の古民家に拠点を置く。
■村上浩康(むらかみ・ひろやす)
宮城県仙台市出身。2000年よりドキュメンタリー映画の製作・監督を続けている。主な作品に『流 ながれ』(文部科学大臣賞)『東京干潟』(新藤兼人賞金賞)『蟹の惑星』(文化庁優秀映画)『たまねこ、たまびと』(2023キネマ旬報文化映画ベストテン第3位)など。新作『あなたのおみとり』を2024年劇場公開予定。