2023
03 02
メディアテーク開館
仙台市民図書館開館
コラム 2024年11月01日更新
会員寄稿文「わたしにとってのドキュメンタリー」Vol.8 山田徹
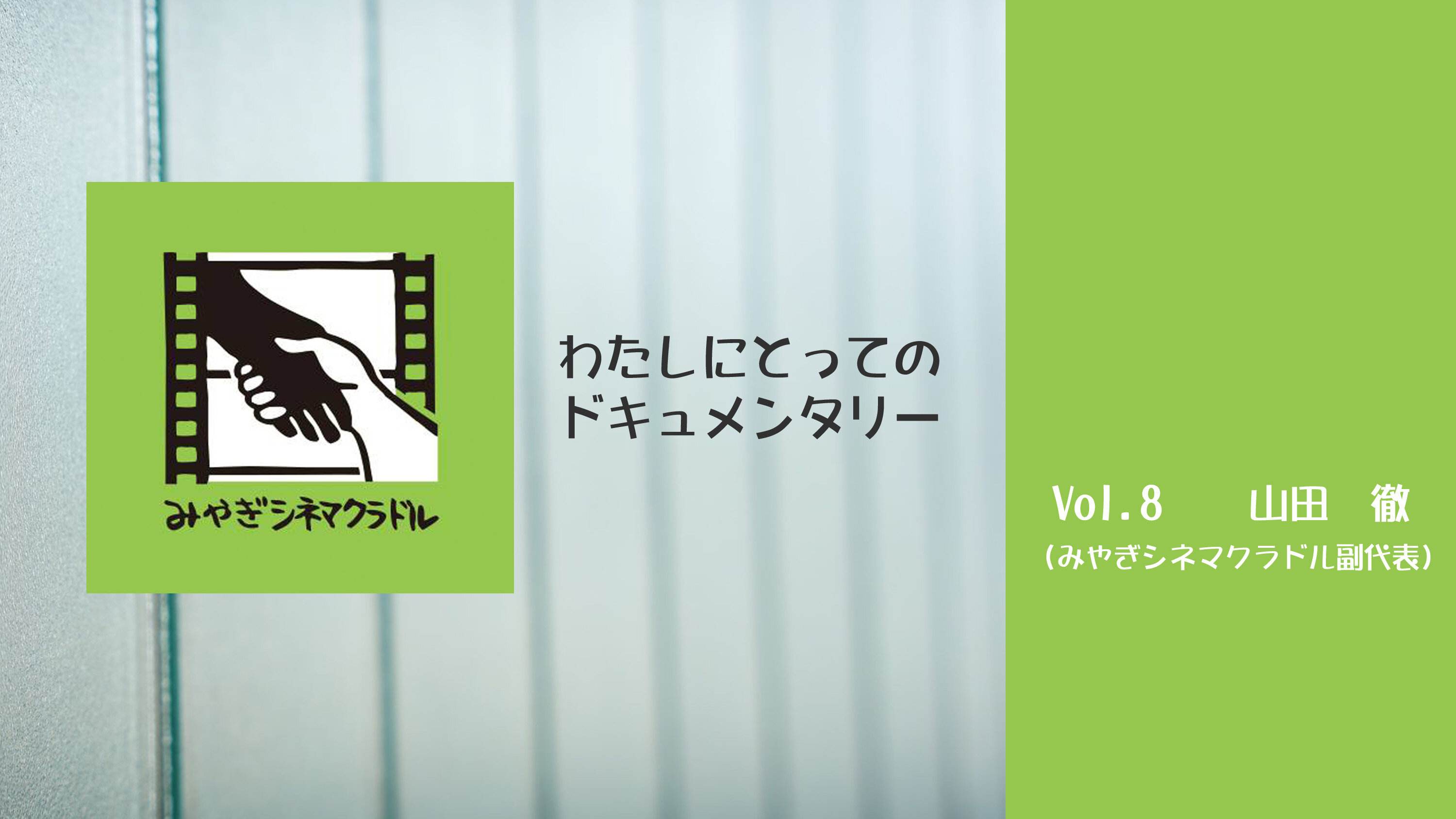
※この企画は、みやぎシネマクラドルの活動をより理解していただくことを目的として、「わたしにとってのドキュメンタリー」をテーマに会員が自由に文章を書く企画です。
**********
ぼくがドキュメンタリー映画の存在を知ったのは大学卒業後のことです。当時、メディア論を研究していたため、関連作品を映画館やレンタル店のDVDで観るようになりました。その中でも特に心に残ったのは、土本典昭監督の水俣シリーズです。患者さんに寄り添い、水俣病の真実を追求する監督の姿勢に胸を打たれました。ぼくにとって、ドキュメンタリーは世界の現実に近づくための重要な手段となりました。
さまざまなドキュメンタリーに触れるうちに、「観るだけでなく作ってみたい」という思いが強まりました。その結果、東京の映画美学校でドキュメンタリー制作を学び、縁あって記録映画作家の羽田澄子監督とプロデューサーの工藤充さんがいる自由工房に勤務する機会に恵まれました。この会社は映画の製作だけでなく、上映や配給活動も手がけていました。羽田さんと工藤さんは、被写体やスタッフとの交友関係を大切にし、この会社でぼくはドキュメンタリーに対する姿勢や情熱、醍醐味を学びました。
2011年の東日本大震災は、ぼくにとって初めての監督作品を作るきっかけになりました。アルバイトで貯めた製作資金を頼りに、夜行バスで被災地に向かい、土地の人々との関係をゼロから築きながら、映画の物語となりそうな出来事を探し回り、時間をかけて撮影を重ねていきました。自主製作でしたが、映画は多くの人々に支えられ、劇場公開に至り、今も上映が続いています。現在は2作目に取り組んでおり、完成が近づいています。
作家としての気づきは、ドキュメンタリーは単なる記録ではなく、再継承の営みであるということです。現実の出来事を素材にした物語を構成するのは、作家と被写体の相互作用によるものです。人であれ風景であれ、被写体は語り部として重要な役割を果たし、作家はその語りの中に潜む動機や意思、記憶や身振りにも触れながら物語を再構成します。この相互関係があってこそ、一つの現実世界、すなわちドキュメンタリーが完成します。
氾濫する情報、AI技術の進展や新しいサイバー空間の出現、分断や画一化が進む現代社会の中で、ドキュメンタリーはどのような役割を果たせるでしょうか。もしドキュメンタリーが世界の現実に近づくための架け橋であるなら、作家が果たすべき役割は、その世界の片隅にいる他者に歩み寄り、そこから生まれる無数の物語と記憶を次世代に継承していくことだと考えています。
**********
山田徹(やまだ・とおる)
東京出身、自由学園卒、映像作家。記録映画作家の羽田澄子監督に師事。東日本大震災後の福島をフィールドに映像制作を行なっている。過去作に映画『新地町の漁師たち』(第3回グリーンイメージ国際環境映像祭・大賞)。現在、映画『あいまいな喪失』(2025年公開予定)を制作中。