2023
03 02
メディアテーク開館
仙台市民図書館開館
コラム 2025年01月15日更新
会員寄稿文「わたしにとってのドキュメンタリー」Vol.11 土屋聡
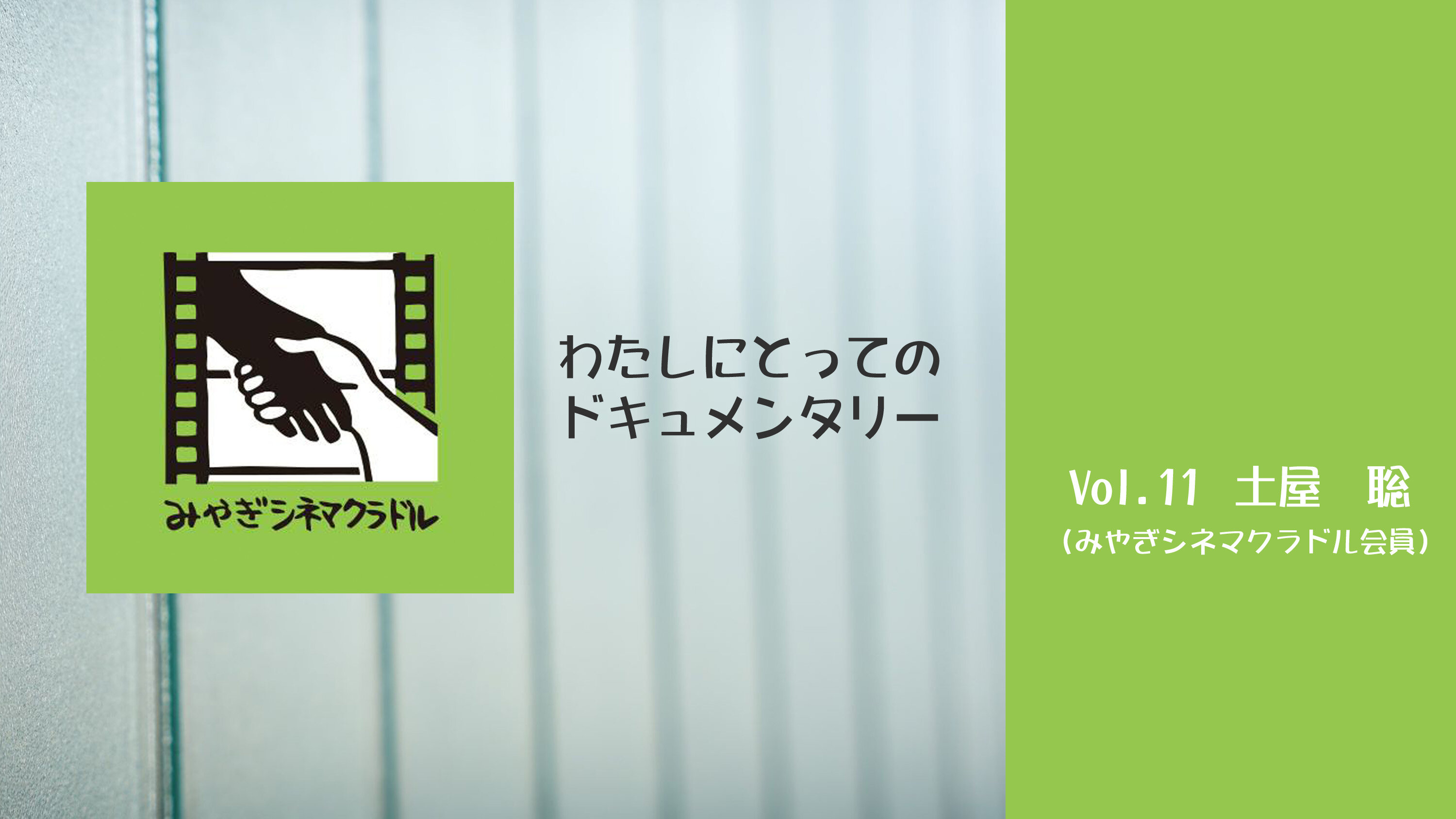
※この企画は、みやぎシネマクラドルの活動をより理解していただくことを目的に、「わたしにとってのドキュメンタリー」をテーマに会員が自由に文章を書く企画です。
**********
1 ジャーナリストになりたかった
1970年代北海道の産炭地で少年時代を過ごした私は、蒸気機関車(SL)を追いかけた。手にはOLYMPUS trip35。炭鉱事故、地底でたくさんの命が奪われた。石炭は見捨てられ、人の暮らしは軽んじられた。幾多の労働闘争、炭鉱閉山は続いた。
ヘイエルダール「コンチキ号漂流記」、本多勝一「極限の民族」、小田実「何でもみてやろう」に出会った。壊されていく炭鉱施設、町、祭りを撮った。
ドキュメンタリー映画との出会いは、毎週木曜午後7時のテレビ番組だった。「驚異の世界」。私は夢見た。冒険をする。撮って書くジャーナリストになる。
2 「ほんとうのこと」のこと
人間は、ひとりでは非力だ。人間は、社会をつくり、知恵を合わせて暮らしてきた。これからもずっとそうだ。氷河期を乗り越えた人間は、たいしたもんだと思う。
知恵というものは、失われる。伝えることで残る。いつどんなことがあったか。事実から知恵を見出す。たくさんの事実がある。いろんな視点によって「ほんとうのこと」が見えてくる。大きな声だけではなく、たくさん流布された言葉だけでなく、小さな事実から「ほんとうのこと」は見えてくる。
3 ドキュメンタリー映画
ドキュメンタリー映画は、動きや音をダイレクトに伝えることができる。時間を伴い、物語ることができる。可能性に満ちている。
世界の何に眼差しを向け、何に聞き耳を立てるか。ドキュメンタリー映画を観る人は、映像作家の眼差しと聞き耳をなぞりながら、新たなものを見出す。理解と誤解の中からも、発見や発明がある。
4 たくさんの「ほんとうのこと」
1980年代、ぴあフィルムフェスティバルに憧れた大学生の頃。8ミリカメラは高額で、手にすることは難しかった。今日、携帯電話で動画撮影ができる。発信することさえ容易だ。幾多の動画が全世界の幾多の人から発し続けられている。事実の氾濫。そんな中、世界の何に眼差しを向け、何に聞き耳を立てるか。何を意図するか。人類の知恵となる「ほんとうのこと」。気付き見極める柔らかさを備えたい。小さな勇気を絶やさないでいたい。
5 視界は広く
私は還暦を迎える。折り返し地点としよう。たくさんの失敗を重ねてきたことを糧として、少年時代の自分をがっかりさせない足取りを進めたい。
若い頃、視界は狭かった。だんだん視野が広がったのは、たくさんの出会いのおかげだ。誰も孤立に陥らず、独りよがりにならないつながりとやり直しのゆとりを築くこと。たくさんの「ほんとうのこと」に照明やマイクを当てる役割を担いたいと思っている。
**********
土屋聡(つちや・さとし)
1965年北海道夕張市出身。宮城県大崎市在住。美術作家。