2023
03 02
メディアテーク開館
仙台市民図書館開館
コラム 2025年03月04日更新
会員寄稿文「わたしにとってのドキュメンタリー」Vol.13 海子揮一
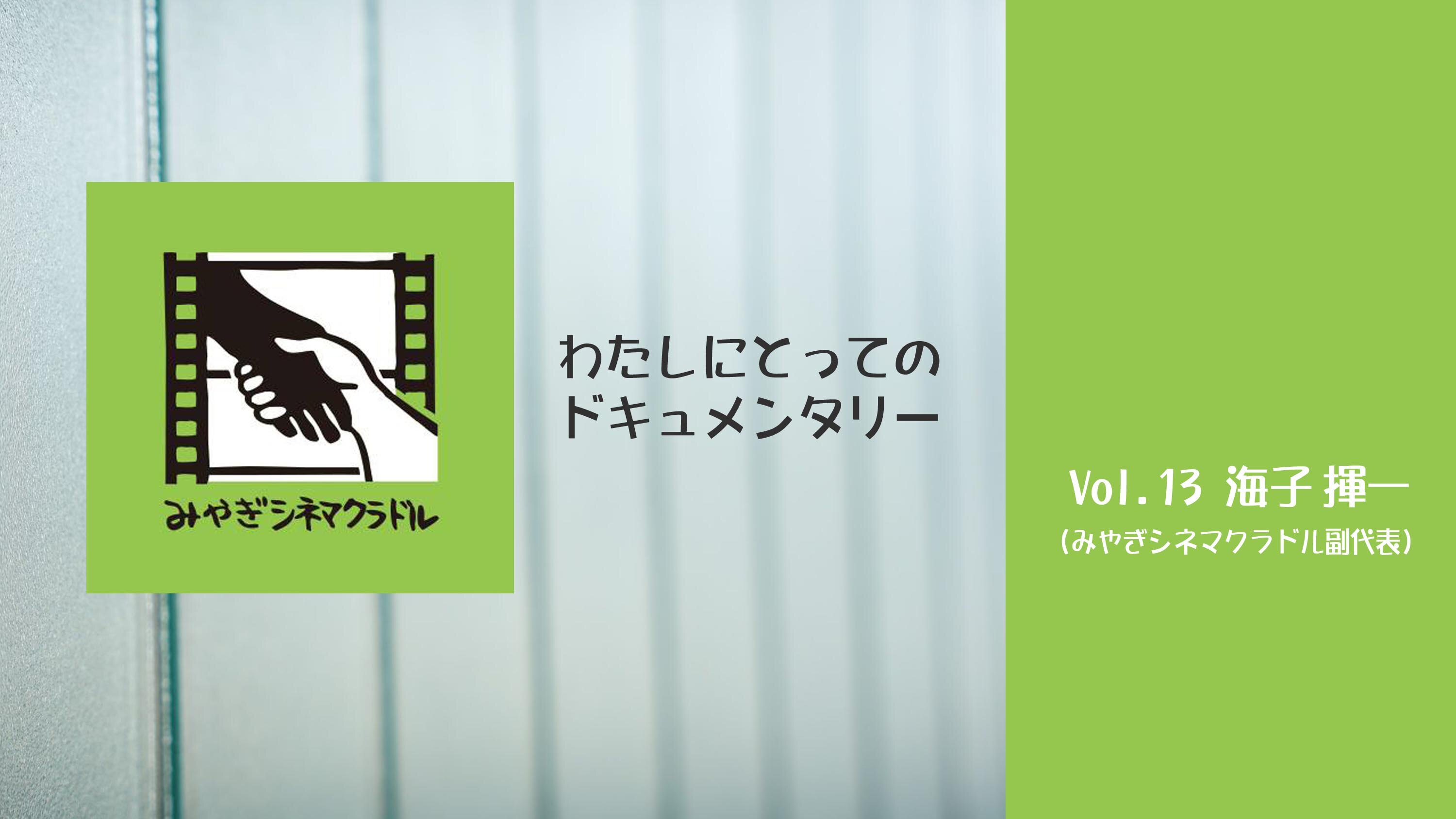
※この企画は、みやぎシネマクラドルの活動をより理解していただくことを目的に、「わたしにとってのドキュメンタリー」をテーマに会員が自由に文章を書く企画です。
**********
いにしえの世の人びとは「歴史」と「詩」を区別していなかったそうです。
物語をたて糸に、コトとコトをよこ糸に、一枚に編みあげられた大きな詩のタピスリーは、王国に属する人びとにとっての神話と心の地図になりました。後世の人びとがそれらを歴史と名付けたのです。
時間というのは相対的なもので、私たちは別々の時間を生きています。ところが「歴史」という考え方が生まれて、時間と物語を分かち合えるようになりました。最初は口伝えで受け継がれていた歴史は集団が大きくなるにつれ、より多くの情報を伝えられるようになっていきました。洞窟の壁に炭やベンガラの絵の具で動物の絵を描いたり、粘土板や木の板に線を刻んだり...そう、「記録とメディア」によってより多くの人びとに、世代を超えて歴史や物語を広めることが可能になったのです。
しかしそれは世界の分断の始まりにもなりました。同じコトでもつなげ方が異なれば、全く別の意味や物語となります。また権力が集中すると「大いなる正しい物語(歴史)」は他の小さな物語を踏み潰してしまうことも起こります。支配された人びとは、やがてその人自身の耳や眼や声で身の回りの風景や出来事を捉えていたことを忘れ、だれかに与えられた物語やことばでしか考えられなくなってしまうのです。とても怖いことですが、これは古代や中世の話だけではありません。むしろ現代のほうが「物語」は急速で過激な荒波となって、世界の人びとの心を揺るがしているのではないでしょうか。
映画や映像も、別々の時間に生きるひとりひとりを「ひとつの時間と物語」につなげる魅力的なメディアですが、一方では信じる物語の違いによって分断や争いを引き起こす力を持っています。それゆえにドキュメンタリーの中には小さな物語を丁寧に描いて、「大きな物語」に抗う人びとの剣と盾となっている作品がたくさん生まれています。
現代社会はますます昏(くら)く不透明になっていく一方ですが、わたしは映画によって「歴史」が生まれる前の詩(うた)を取り戻せたら...と考えるときがあります。スクリーンの向こう側の風景や人物に声や体温を感じたり、観終わってだれかと語り合う時間の中に、わたし自身の生の在りかを見つけるのです。
わたしにとってドキュメンタリーとは未知なる他者や未来と出会うための灯火になっています。そして、暗やみの洞窟の壁画は、人が灯す松明(たいまつ)の光があって見えてくるように、映画と人が共にある空間も同じくらい大切だと考えています。
**********
海子揮一(かいこ・きいち)
1970年宮城県出身。建築家/ブリコルール/クリエーター。環境とコミュニティをテーマにした建築設計活動の傍ら、映像製作・イベント企画・造形デザインも手掛ける。より自然に近い環境を求めて、2018年より仙台市に隣接する村田町寒風沢の古民家に拠点を置く。